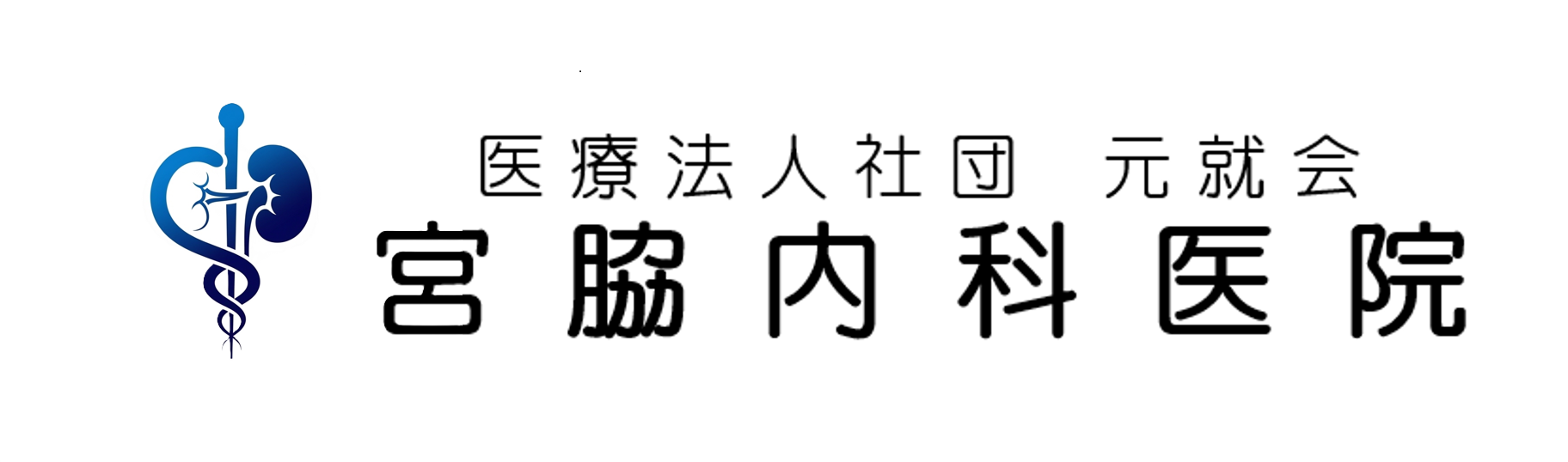ニュース詳細WHAT's NEW

ニュース詳細WHAT's NEW

減量 2025.07.10
「“太りやすさ”は遺伝子で決まる?肥満の個人差とその背景」
肥満には遺伝的な要因が関わっていることが知られており、肥満関連遺伝子の存在が確認されています。
これらの遺伝子は、食欲の調整、エネルギー代謝、脂肪の蓄積などに関与しており、その遺伝子型によって太りやすさや脂肪のつきやすい部位に違いが出ることがわかっています。
肥満関連遺伝子の種類
現在、50種類以上の肥満関連遺伝子が確認されていますが、特に日本人で注目されている主な遺伝子としては以下のものがあります。
-
●ADRB3(β3アドレナリン受容体)遺伝子:
-
ノルアドレナリンというホルモンの受容に関わり、脂肪の分解や燃焼に影響します。
-
この遺伝子に変異があると、内臓脂肪が蓄積されやすく、ウエスト周りから太りやすい傾向があると言われています(洋なし型)。
-
-
●UCP1(脱共役タンパク質1)遺伝子:
-
褐色脂肪細胞における熱産生に関与しています。
-
この遺伝子に変異があると、体温が低下した際に皮下脂肪を燃焼させる効率が悪く、脂質を摂りすぎると太りやすい傾向があると言われています(バナナ型)。
-
-
●ADRB2(β2アドレナリン受容体)遺伝子:
-
アドレナリンというホルモンの受容に関わり、脂肪の分解や燃焼に影響します。
-
この遺伝子に変異があると、特にタンパク質をエネルギーとして早く消費してしまう傾向があり、筋肉がつきにくい傾向があると言われています(りんご型)。
-
その他にも、以下のような遺伝子が肥満に関連するとされています。
-
●FTO遺伝子: 脂肪量や肥満と関連が深く、この遺伝子の変異がある場合、食欲が増進しやすく、体脂肪が増加しやすい傾向があります。
-
●MC4R遺伝子: 満腹感や食欲の調整に関わり、変異があると食欲が増し、エネルギー消費が抑制されやすい傾向があります。
-
●PPARG遺伝子: 脂肪細胞の生成や脂肪の代謝に関与し、変異があると脂質代謝に影響を与え、脂肪が蓄積しやすくなる可能性があります。
-
●FABP2遺伝子: 脂肪酸の吸収や代謝に関与し、変異があると脂質の吸収が高まりやすくなるとされています。
遺伝的要因と環境要因
肥満は遺伝的要因だけでなく、生活習慣(食生活、運動習慣など)といった環境要因が複雑に絡み合って発症する多因子疾患です。一般的には、肥満の要因のうち約3割が遺伝的素因、約7割が環境因子によるものと考えられています。
両親が肥満である場合、子どもも肥満になりやすい傾向がありますが、これは遺伝子だけでなく、家族の食生活や運動習慣といった生活環境も大きく影響しているためです。
肥満遺伝子検査
近年では、唾液や頬の粘膜を採取するだけで、上記の肥満関連遺伝子を解析し、個人の肥満タイプや太りやすい傾向を調べることができる肥満遺伝子検査が普及しています。これにより、以下のようなメリットが期待されています。
-
●自身の太る原因の把握: 遺伝的な体質を知ることで、なぜ太りやすいのか、脂肪がどこにつきやすいのかを理解できます。
-
●最適なダイエット法の提案: 遺伝子型に基づいた、個々に合った食事や運動のアドバイスを得られます。例えば、糖質代謝が苦手なタイプには糖質制限、脂質代謝が苦手なタイプには脂質制限など、より効率的なダイエット方法が見つかる可能性があります。
-
●生活習慣病の予防: 自身の体質を理解し、それに合わせた生活習慣を送ることで、将来的な生活習慣病のリスクを低減することにも繋がります。
肥満関連遺伝子の研究は現在も進んでおり、そのメカニズムのさらなる解明や、より効果的な肥満予防・治療法への応用が期待されています。